株式投資の世界に足を踏み入れたばかりの初心者にとって、投資した株の価値が突然大きく下がる「暴落」は、非常に不安な出来事かもしれません。何も理解していない状況で暴落に直面すると、どのように対応すべきか分からず、狼狽してしまうこともあるでしょう。本稿では、株式投資における暴落とは何か、なぜ起こるのか、そして暴落時に初心者が取るべき行動について、分かりやすく解説します。暴落を正しく理解し、冷静に対処することで、長期的な投資の成功につなげることが可能です。本稿では、暴落の定義から、過去の事例、そのメカニズム、そして具体的な対応策までを網羅的に解説していきます。
「暴落」とは?
株式投資における「暴落」(ぼうらく)とは、市場全体の広範囲にわたり、株価が短期間に大幅に下落する現象を指します 。暴騰とは反対に、大量の売り注文が殺到し、買い注文が不足することで株価が急激に値下がりする状態です 。一般的には、数年に一度あるかないかの厳しい下落というイメージで捉えられています 。
株価がどれくらい下がれば暴落と定義されるのかについて、明確な基準はありません 。しかし、一般的には、主要な株価指数(例えば日経平均株価)が1日に10%以上下落するような場合、過去の下落率ランキングでも上位に入るほどの大きな変動であるため、「暴落」と呼ぶにふさわしいと言えるでしょう 。5%以上の下落は「急落」、数日から数週間で20%以上の下落は「市場崩壊」と呼ばれることもあります 。
暴落時には、業績の良い銘柄も含めて多くの銘柄が大幅な下落に見舞われ、市場全体が全面安となるのが特徴です 。しかし、後から振り返ってみると、このような暴落時こそ、注目していた銘柄を安く購入できる絶好の機会となることもあります 。
市場の急激な下落には様々な程度のものがあり、「暴落」という言葉の捉え方は人によって異なる可能性があります。しかし、主要な株価指数が短期間に二桁パーセントで下落するような状況は、一般的に「暴落」として認識されます。また、市場の状況をより細かく理解するために、「急落」や「市場崩壊」といった言葉も知っておくと良いでしょう。
過去の日本の株式市場における暴落事例
日本の株式市場においても、過去に何度か大きな暴落が発生しています。これらの事例を知ることは、現在の市場の動きを理解し、将来の暴落に備える上で役立ちます。
| 年 | 出来事(原因) | 日経平均株価の近似下落率 |
|---|---|---|
| 1987 | ブラックマンデー(米国市場の暴落、国際協調の乱れ) | 14.9% |
| 1990 | バブル崩壊(資産バブルの終焉) | 日経平均株価の歴代下落率トップ5に入る下落を3度記録 |
| 2001 | 米国同時多発テロ事件(米国でのテロ攻撃) | 6.6% |
| 2008 | リーマンショック(米国大手金融機関の破綻による世界的な金融危機) | バブル崩壊後の最安値7,054.98円まで下落 |
| 2020 | コロナショック(新型コロナウイルスの世界的な感染拡大と経済活動の停止) | 約30% |
| 2024 | 8月の歴史的な乱高下(米国経済の減速懸念、円高、日銀の政策金利引き上げ) | 12.4% |
この表は過去の主な暴落事例を示しており、個別の銘柄ではさらに大きな下落を経験している可能性もあります 。例えば、1987年のブラックマンデーは、前日に米国ダウ平均が約22%も下落したことがきっかけとなり、翌日の日経平均株価は史上最大の14.9%という大暴落を記録しました 。1990年のバブル崩壊では、1989年末に史上最高値をつけた日経平均が、翌年に3度も大きな暴落を経験し、その後も株価は低迷を続けました 。2008年のリーマンショックでは、アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻が世界的な経済の混乱を招き、日経平均株価も大きく下落しました 。2020年のコロナショックでは、世界的なロックダウンにより経済活動が停止し、日経平均株価は一時約30%も下落しましたが、その後、世界的な金融緩和などの影響で急速に回復しました 。
過去の暴落事例を振り返ると、その原因は国内外の様々な要因に起因しており、日本の株式市場がグローバルな経済や政治情勢と深く結びついていることが分かります。過去の暴落を知ることで、市場の変動は避けられないものであり、一時的な下落の後には回復する可能性もあるということを理解できるでしょう。
なぜ株価は急落するのか?
株価が短期間に大きく下落する暴落には、複数の要因が複雑に絡み合っています。初心者がこれらのメカニズムを理解することは、暴落時に冷静に対応するために重要です。
経済指標の悪化
経済成長率の低下、失業率の上昇、消費者信頼感の低下、製造業の不振など、経済状況が悪化を示すニュースは、企業の将来の収益に対する投資家の悲観的な見方を強める可能性があります 。例えば、米国の経済指標が予想を下回る結果となった場合、米国経済の減速懸念が高まり、日本市場にも影響を与えることがあります 。また、日本銀行や米連邦準備制度理事会(FRB)といった中央銀行による金利の変更は、企業の借入コストや経済全体の成長見通しに影響を与え、株価の変動要因となります 。景気の先行きに対する不透明感が増すと、投資家は株式の価値を再評価し、売却する動きが広がりやすくなります。経済の基礎的な状況が悪化すると、企業の収益が低下する可能性が意識され、広範囲にわたる売り圧力につながります。
地政学的なリスク
戦争、政治的な不安定、国際的な緊張、貿易関係の変化といった地政学的なリスクの高まりは、世界経済の不確実性を増大させ、投資家心理を悪化させる要因となります 。中東情勢の悪化などが株式市場に悪影響を与える例もあります 。地政学的なリスクは、サプライチェーンの混乱、コストの増加、世界経済の成長への懸念などを引き起こす可能性があり、投資家はリスクを回避する動きを強めます。政治的な不安定さによって引き起こされる不確実性は、投資家の信頼感を揺るがし、株式のようなリスク資産からより安全な資産への資金移動を促します。
市場心理の変化
投資家の感情、特に恐怖心や楽観主義は、市場の動きに大きな影響を与えます 。大きなマイナスの出来事や悪いニュースが続くと、市場の雰囲気は楽観から悲観へと一変し、売りが先行するようになります 。特に、株価が下落し始めると、「狼狽売り」(ろうばいり)と呼ばれる、さらなる損失を恐れた投資家によるパニック的な売りが増加し、株価の下落に拍車をかけることがあります 。このように「売りが売りを呼ぶ」連鎖反応によって、株価は急激に下落することがあります 。市場心理は時に過剰に反応し、ファンダメンタルズ(企業の基礎的な価値)とはかけ離れた価格変動を引き起こすこともあります 。投資家は感情に左右されず、事実に基づいて冷静な判断を心がける必要があります。
連鎖的な影響
グローバル化が進んだ現代の金融市場では、ある市場で発生した暴落が、国境を越えて他の市場へと連鎖的に波及する可能性があります 。例えば、米国市場で株価が大きく下落すると、その影響はすぐに東京市場にも及ぶことがあります 。また、近年では、コンピュータによる自動売買システムやアルゴリズム取引が普及しており、これらが市場のボラティリティ(価格変動の大きさ)を増幅させ、連鎖的な売り注文を誘発する可能性も指摘されています 。世界経済の相互依存性が高まっているため、一つの地域や主要な市場で発生したネガティブな出来事は、たとえ直接的な経済的影響が限定的であっても、他の市場の投資家心理を悪化させ、同様の動きを引き起こすことがあります。
暴落時に初心者が取るべき行動:冷静に対処するために
株式市場が暴落した時、初心者にとって最も重要なことは、感情に流されず冷静に対処することです。
冷静さを保つ
市場が大きく下落すると、誰でも不安になるものですが、ここでパニックに陥って感情的な判断をすることは避けるべきです 。深呼吸をして、まずは落ち着きましょう。そして、なぜ自分が株式投資を始めたのか、長期的な目標は何なのかを思い出してください。2024年8月の株価急落の際にも、慌てて売却した投資家は、その後の株価の反発で損失を確定させてしまう結果となりました 。市場の短期的な変動に一喜一憂せず、冷静に状況を分析することが大切です 。
狼狽売りをしない
暴落時に最もやってはいけないことの一つが、恐怖心から保有している株を売ってしまう「狼狽売り」です 。狼狽売りは、損失を確定させてしまうだけでなく、その後の市場の回復から利益を得る機会を失うことにもつながります 。過去の歴史を振り返っても、株式市場は暴落の後には必ず回復してきています 。一時的な株価の下落に過剰に反応せず、長期的な視点を持つことが重要です。
長期的な視点を持つ
株式投資は一般的に、短期的な売買で利益を得ることを目的とするのではなく、長期的な資産形成を目的として行うものです 。短期的な市場の変動に惑わされず、自分が投資した企業の成長性や、長期的な経済の動向を見据えるようにしましょう。暴落は、長期的な投資の道のりにおける一時的な出来事と捉え、焦らずに市場の回復を待つことが大切です。
積立投資を継続する
もしあなたが毎月一定額を積み立てて株式や投資信託を購入する「積立投資」を行っているなら、暴落時こそその積み立てを継続することをおすすめします 。株価が下落している時には、同じ金額でもより多くの株数や投資信託の口数を購入できるため、平均購入単価を下げる効果(ドル・コスト平均法)が期待できます 。暴落時に積み立てを止めてしまうと、この恩恵を受けることができなくなってしまいます 。
買い増しを検討する(ただし慎重に)
長期的な視点を持ち、かつ当面使う予定のない「余剰資金」があるならば、暴落は優良な株や投資信託を割安な価格で購入できるチャンスと捉えることもできます 。ただし、何も考えずに買い増しをするのは危険です 。まずは少額から試しに購入してみる「打診買い」という方法も有効です 。また、業績が悪化した企業の株を安易に「ナンピン買い」(平均購入単価を下げるために買い増すこと)するのは、さらに損失を拡大させる可能性があるため、慎重に検討しましょう 。
ポートフォリオを見直す
暴落は、自身の投資ポートフォリオを見直し、長期的な目標やリスク許容度と照らし合わせて、現状の配分が適切かどうかを確認する良い機会となります 。株式と債券の比率、投資先の分散状況などを再検討しましょう。ただし、暴落の最中に慌ててポートフォリオを大きく変更するのではなく、市場が落ち着きを取り戻してから調整を行うのが賢明です 。
暴落の可能性を事前に予測するための指標と分析
株式投資を行う上で、暴落の可能性を事前に知ることができれば、適切な対策を講じることができます。しかし、株式市場の暴落を正確に予測することは一般的に非常に困難であることを理解しておく必要があります 。プロの投資家やアナリストであっても、常に暴落を予測できるわけではありません 。
予測の難しさ
市場の動きは多くの要因によって左右されるため、完全に予測することは不可能です。暴落は、予期せぬ出来事(ブラック・スワン)によって引き起こされることも少なくありません。したがって、誰かが「必ず暴落する」といった断定的な予測をしている場合でも、鵜呑みにしないように注意が必要です。市場の予測に頼るのではなく、常にリスク管理を意識した投資を行うことが重要です。
注意すべき指標の例
暴落を確実に予測することはできませんが、市場の状況を把握し、リスクが高まっている可能性を示すいくつかの指標は存在します。
- 景気後退の兆候: 一般的に、景気後退は企業の業績悪化につながり、株価の下落要因となります 。景気後退の兆候として注目される指標には、「逆イールド」(短期金利が長期金利を上回る現象)があります 。その他、製造業景況感指数(ISM指数)の低下 、失業保険申請件数の増加 、消費者信頼感の低下 なども、景気後退の可能性を示す指標として知られています。ただし、これらの指標が必ずしも株価暴落を予測するわけではなく、タイミングも一定ではありません 。
- 市場の過熱感を示す指標: 市場が過度に買われている状態を示す指標も、暴落の可能性を考える上で参考になります 。例えば、「騰落レシオ」は、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率を示す指標で、一般的に120%を超えると過熱気味とされることがあります 。また、「RSI(相対力指数)」は、買われすぎや売られすぎを示す指標で、70%を超えると買われすぎの水準とされることがあります 。さらに、「25日移動平均線との乖離率」も、株価が短期的に大きく変動しているかどうかを見る指標の一つです 。これらの指標は、市場が調整局面に入る可能性を示唆するものであり、必ずしも暴落を意味するわけではありません 。
- 恐怖指数(VIX指数): VIX指数は、S&P 500指数の将来の変動予想を示す指数で、投資家の不安心理の度合いを示すとされています 。VIX指数が急上昇した場合、市場の先行きに対する不安心理が高まっている可能性があり、株価が下落する兆候と見られることがあります 。一般的に、VIX指数が30や40を超えると警戒水準と言われています 。ただし、VIX指数の上昇が必ずしも暴落につながるわけではなく、一時的なボラティリティの上昇である場合もあります。
- 株価チャート分析: 一部の投資家は、「移動平均線」やトレンドラインといった株価チャートの分析(テクニカル分析)を用いて、市場の転換点を探ろうとします 。例えば、株価が移動平均線を下抜けた場合、下降トレンドへの転換を示すと解釈されることがあります 。しかし、テクニカル分析は過去の株価の動きに基づいたものであり、将来の予測を保証するものではありません。特に、予測不可能な出来事が引き起こす暴落を予測することは困難です。
これらの指標は、市場の状況を多角的に把握するための参考情報として活用できますが、それだけに頼って暴落を予測しようとするのは避けるべきです。初心者の方は、市場の動向を注意深く見守りつつ、長期的な投資戦略とリスク管理に重点を置くことが重要です。
暴落を投資のチャンスと捉える:逆張りの考え方
市場が大きく下落する暴落は、見方を変えれば投資のチャンスと捉えることもできます。「逆張り」(ぎゃくばり)という投資戦略は、まさにこの考え方に基づいています 。
逆張り投資の考え方
逆張り投資とは、市場の多数派とは逆の行動を取る投資戦略です 。暴落時には、多くの投資家が恐怖を感じて株を売る傾向にありますが、逆張り投資家は、このような状況を割安になった株を買い入れる好機と捉えます 。投資の基本原則である「安く買って、高く売る」を実践する上で、暴落は絶好の機会となる可能性があるのです 。市場が過剰に悲観的になっている時には、本来の価値よりも大幅に安く評価されている優良な企業が存在する可能性があります。
暴落時に注目すべき投資戦略
暴落時に投資のチャンスを見出すためには、いくつかの戦略が考えられます。
- 質の高い株への投資: 暴落時には、業績が安定しており、財務状況も健全な優良企業の株価も、市場全体の流れに押されて下落することがあります 。このような企業は、長期的に見れば株価が回復する可能性が高いため、暴落時に注目すべき投資対象となります 。自己資本比率が高く、配当利回りの高い銘柄なども、暴落時の買い付け候補として考えられます 。
- 投資信託の活用: 個別株の選定に自信がない初心者の方には、広範囲の銘柄に分散投資されているインデックスファンドや、多様な資産に投資するバランス型の投資信託などがおすすめです 。暴落時にこれらの投資信託を積み立てで購入することで、より多くの口数を割安な価格で取得できる可能性があります。
- 段階的な買い付け: 一度にまとまった金額を投資するのではなく、株価の変動を見ながら段階的に買い進める「打診買い」という手法も有効です 。これにより、底値を捉える難しさを回避し、リスクを分散することができます。市場の底を正確に予測することはほぼ不可能であることを理解しておきましょう 。
- 長期投資の継続: すでに長期投資を行っている場合は、暴落を単に保有株を安く買い増すチャンスと捉え、投資戦略を継続することが重要です 。短期的な市場の変動に惑わされず、長期的な視点を維持しましょう 。
暴落時に冷静かつ戦略的に投資を行うことで、市場が回復した際に大きな利益を得られる可能性があります。
注意点
逆張り投資は、市場の反発を期待して行うものですが、株価がすぐに回復するとは限りません 。場合によっては、さらに下落する可能性もあるため、リスクを十分に理解しておく必要があります。初心者の方は、自分が投資する企業の事業内容や財務状況をしっかりと理解し、かつ当面使う予定のない「余剰資金」で投資を行うように心がけましょう 。自身のリスク許容度を考慮しながら、慎重に判断することが大切です。
暴落に備えて普段からできるリスク管理
株式市場の暴落は予測が難しいものですが、日頃から適切なリスク管理を行うことで、暴落時の損失を抑え、精神的な負担を軽減することができます。
分散投資の徹底
投資のリスクを低減するための最も基本的な方法の一つが、分散投資です 。異なる種類の資産(株式、債券、不動産、金など)に投資することで、一つの資産の価格が下落した場合でも、他の資産で損失をカバーできる可能性があります 。また、投資地域を分散することも重要です。国内だけでなく、海外の株式や債券にも投資することで、特定の国の経済状況に左右されるリスクを軽減できます 。さらに、投資のタイミングを分散する「時間分散」も有効です。毎月一定額を積み立てる「積立投資」は、時間分散の代表的な方法です 。
余剰資金での投資
生活に必要な資金や、近いうちに使う予定のある資金を投資に回すのは避けるべきです 。投資は、あくまで当面使う予定のない「余剰資金」で行うようにしましょう。これにより、暴落時に予期せぬ出費が必要になった場合でも、損失を確定させるために慌てて売却する必要がなくなります。
投資ルールの設定と遵守
株式投資を始める前に、自分なりの投資ルールを設定しておくことが重要です 。例えば、「株価が〇%下落したら売却する(損切り)」、「〇%の利益が出たら利益を確定する」、「ポートフォリオの資産配分を定期的に見直す」といったルールを決めておき、市場が大きく変動した時でも感情に左右されずにルールに従って行動することで、リスクをコントロールすることができます。
リスク許容度を把握する
自分がどれくらいの損失に耐えられるのか(リスク許容度)を理解しておくことは、適切な投資戦略を立てる上で非常に重要です 。リスク許容度を超えた投資を行うと、市場が下落した際に過度なストレスを感じ、冷静な判断ができなくなる可能性があります。自分のリスク許容度に合った投資を行うように心がけましょう。
長期的な視点を維持する
繰り返しになりますが、株式投資は短期的な利益を追求するのではなく、長期的な資産形成を目的とするものです 。短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持って投資を続けることが、暴落に備えるための最も重要な心構えと言えるでしょう。
まとめ
株式投資における暴落は、初心者にとって大きな試練となる可能性があります。しかし、暴落のメカニズムを理解し、過去の事例から学び、適切な行動を取ることで、冷静に対処することができます。最も重要なことは、パニックにならず、長期的な視点を持ち続けることです。分散投資を徹底し、余剰資金で投資を行い、自分自身の投資ルールを守ることで、暴落のリスクを軽減し、長期的な投資の成功につなげることができるでしょう。市場の変動は避けられないものですが、しっかりと準備をして臨めば、それは長期的な資産成長の機会にもなり得ます。

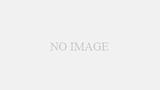
コメント