株式投資の世界へ足を踏み入れたばかりの皆様にとって、株価がどのように変動するのか、そしてどのように投資判断を下せば良いのかは、大きな関心事でしょう。株価の動きを予測し、より良い投資成績を目指すための分析手法はいくつか存在しますが、その中でも特に重要なのが「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」です。本稿では、株式投資の初心者の方に向けて、テクニカル分析と対比させながら、ファンダメンタルズ分析とは何かをわかりやすく解説します。さらに、テクニカル分析の代表的な指標を5つ紹介し、その基本的な見方や使い方を解説していきます。
ファンダメンタルズ分析とは
ファンダメンタルズ分析とは、企業の「本質的な価値」を評価する分析手法です 。企業の財務状況、経営状態、業界の動向、そして経済全体の状況などを詳しく分析することで、その企業の株価が割安なのか割高なのかを判断し、中長期的な投資判断に役立てます 。具体的には、企業の売上高、利益、資産、負債などの財務諸表を分析したり、経営者の質や経営戦略を評価したりします。また、その企業が属する業界の成長性や競争環境、さらには国の経済成長率や金利、為替レートといったマクロ経済の要因も考慮に入れます 。ファンダメンタルズ分析は、企業の長期的な成長性や収益性に着目するため、数ヶ月、数年といった比較的長い期間での投資を考えている方にとって非常に重要な分析手法となります。過去の出来事や経済データなど、数値的に評価できる情報に基づいて分析を行うのが特徴です 。
テクニカル分析とは
一方、テクニカル分析とは、過去の株価の値動きや取引量(出来高)のパターンを分析し、将来の株価の変動を予測する手法です 。テクニカルアナリストは、主に株価チャートを用いて、過去の値動きの中に現れる規則性やトレンドを見つけ出し、それを基に将来の値動きを予測しようとします 。過去の値動きは、市場参加者(投資家やトレーダー)の心理状態や行動の結果が反映されたものと考えられており 、テクニカル分析はこの心理的な要因も考慮に入れていると言えます。テクニカル分析は、短期的な売買タイミングを計るのに役立つと考えられていますが 、長期的なトレンド分析にも応用できます。
テクニカル分析とファンダメンタルズ分析:主な違い
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析は、株価を分析するアプローチが大きく異なります。ファンダメンタルズ分析が企業の「価値」に焦点を当てるのに対し、テクニカル分析は株価の「動き」そのものに注目します 。
| 特徴 | ファンダメンタルズ分析 | テクニカル分析 |
|---|---|---|
| 焦点 | 企業の本来の価値 | 株価の動きと取引量 |
| 使用データ | 財務諸表、経済指標、業界データ | 株価チャート、取引量、テクニカル指標 |
| 時間軸 | 中長期 | 短期~中期(長期にも応用可能) |
| 分析の目的 | 企業は割安か割高か? | トレンドは?いつ売買すべきか? |
ファンダメンタルズ分析は、なぜ株価が変動するのか(企業の本質的な価値に基づく理由)を探るのに対し、テクニカル分析は、株価が実際にどのように動いているのか(価格のパターン)を分析します 。為替取引においては、ファンダメンタルズ分析は中長期的な視点で、テクニカル分析は短期的な視点で活用される傾向があります 。テクニカル分析は、過去の出来事や経済データといった数値化が難しい要素を考慮せずに相場を分析するため、現在の市場の状況を素早く把握するのに役立ちます 。しかし、両者の最終的な目標は同じで、「より高い収益を上げ、損失を最小限に抑える」ことです 。投資判断においては、どちらか一方に偏るのではなく、両方の分析手法をバランス良く活用することが重要です 。
テクニカル分析の基本原則
テクニカル分析には、一般的に以下の3つの基本原則があると考えられています 。
- チャートは市場の動きをすべて織り込む: この原則は、株価チャートには、市場におけるすべての情報、つまり企業の業績、経済状況、投資家の心理など、株価に影響を与えるあらゆる要因がすでに反映されているという考え方です 。したがって、テクニカル分析では、チャートの形状や動きを分析することによって、将来の株価を予測できると考えます。
- 価格の動きはトレンドを形成する: 株価は、一定期間にわたって同じ方向に動き続ける傾向があります。これを「トレンド」と呼びます。トレンドには、上昇トレンド、下降トレンド、そして横ばいのトレンドがあります 。テクニカル分析では、現在のトレンドを把握し、そのトレンドが継続する可能性が高いと考えることで、将来の価格の動きを予測しようとします。
- 歴史は繰り返す: 過去の株価のパターンや市場の行動は、投資家の心理が繰り返されるため、将来においても同様のパターンが現れる傾向があると考えられています 。テクニカル分析では、過去のチャートパターンを分析し、類似のパターンが現在現れている場合に、過去の経験則に基づいて将来の値動きを予測しようとします。
代表的なテクニカル指標
テクニカル分析では、過去の株価や出来高のデータに基づいて計算される様々な指標(グラフやライン)を用いて、将来の値動きを予測します 。これらのテクニカル指標は、大きく分けて「トレンド系」と「オシレーター系」の2種類に分類されます 。
- トレンド系指標: 相場の方向性、つまりトレンドの発生や転換などを分析するために用いられます。
- オシレーター系指標: 相場の買われすぎや売られすぎといった過熱感を判断するために用いられます。
以下に、株式投資の初心者にも比較的理解しやすい代表的なテクニカル指標を5つ紹介します。
1. 移動平均線(MA)
移動平均線は、過去の一定期間の株価(通常は終値)の平均値を線で結んだものです 。株価の変動のノイズを取り除き、トレンドの方向性を視覚的に捉えることができるため、多くの投資家に利用されています 。
種類: 最も一般的なのは、一定期間の終値の単純な平均値を結んだ 単純移動平均線(SMA) です 。その他にも、直近の価格に重みを置いて計算する 指数平滑移動平均線(EMA) や 加重移動平均線(WMA) などがあります 。EMAやWMAは、SMAよりも直近の価格変動に敏感に反応する傾向があります 。
期間: 移動平均線を計算する期間は、投資家の目的や分析する時間軸によって異なります。一般的には、短期的なトレンドを見るには5日や10日、中期的なトレンドを見るには20日、25日、50日、75日、長期的なトレンドを見るには100日や200日といった期間が用いられます 。
見方・使い方:
- トレンドの把握: 移動平均線が上向きであれば上昇トレンド、下向きであれば下降トレンド、横ばいであればレンジ相場と判断できます 。
- トレンドの強さ: 移動平均線と株価の位置関係から、トレンドの強さを判断できます。一般的に、株価が移動平均線よりも上にある場合は上昇トレンドが強い、下にある場合は下降トレンドが強いとされます 。
- サポートライン・レジスタンスライン: 上昇トレンドでは、株価が一時的に下落しても移動平均線付近で反発することがあり、この移動平均線がサポートライン(下値支持線)として機能することがあります。逆に、下降トレンドでは、株価が一時的に上昇しても移動平均線付近で再び下落することがあり、この移動平均線がレジスタンスライン(上値抵抗線)として機能することがあります 。
- ゴールデンクロス・デッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けることを「ゴールデンクロス」といい、上昇トレンドへの転換を示す買いサインとされます 。一方、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けることを「デッドクロス」といい、下降トレンドへの転換を示す売りサインとされます 。例えば、50日移動平均線と200日移動平均線の組み合わせは、中長期的なトレンドの転換を捉えるためによく用いられます 。
2. MACD(マックディー)
MACDは、トレンドの方向性と相場の過熱感を同時に判断できるテクニカル指標です 。日本語では「移動平均収束拡散」と呼ばれ、トレンド系とオシレーター系双方の性質を持っています 。
構成: MACDは、主に以下の3つの要素で構成されています :
- MACDライン: 短期(通常12日)のEMAから長期(通常26日)のEMAを引いたものです 。
- シグナルライン: MACDラインの移動平均線(通常9日間のEMA)です 。
- ヒストグラム: MACDラインとシグナルラインの差を棒グラフで表示したものです 。
見方・使い方:
- ゴールデンクロス・デッドクロス: MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜ける(ゴールデンクロス)と、買いのタイミングと判断されます 。逆に、MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜ける(デッドクロス)と、売りのタイミングと判断されます 。
- ゼロライン: MACDラインとシグナルラインがともにゼロラインよりも上にある場合は、上昇トレンドが強いとされ 、逆にゼロラインよりも下にある場合は、下降トレンドが強いとされます 。
- ダイバージェンス: 株価が上昇しているのにMACDラインが下降している、あるいはその逆の現象が起こった場合、トレンドの転換が近い可能性があるとされます 。
3. RSI(相対力指数)
RSIは、一定期間における株価の値上がり幅と値下がり幅の比率を計算し、相場が買われすぎか売られすぎかを判断するのに用いられるオシレーター系の指標です 。RSIの数値は0%から100%の間で変動します 。
計算方法: RSIは、一定期間の上昇幅の合計を、上昇幅の合計と下落幅の合計を足したもので割って算出されます 。一般的には、14日間の期間が用いられます 。
見方・使い方:
- 買われすぎ・売られすぎの判断: 一般的に、RSIが70%以上になると買われすぎと判断され、そろそろ価格が下落に転じる可能性が示唆されます 。一方、RSIが30%以下になると売られすぎと判断され、価格が上昇に転じる可能性が示唆されます 。ただし、強いトレンドが発生している場合は、RSIが70%や30%の水準を超えてもトレンドが継続することがあるため注意が必要です 。
- ダイバージェンス: 株価が上昇しているのにRSIが下降している、あるいはその逆の現象が起こった場合、トレンドの転換が近い可能性があるとされます 。
4. ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、移動平均線とその上下に標準偏差に基づいて描かれた帯で構成されるテクニカル指標です 。一般的には、20日間の単純移動平均線を中心線とし、その上下に±2標準偏差のバンドが表示されます 。
構成: ボリンジャーバンドは、以下の3本の線で構成されています :
- 中心線(ミドルバンド): 通常、20日間の単純移動平均線が用いられます 。
- アッパーバンド: 中心線に標準偏差の2倍を加えた線です 。
- ローワーバンド: 中心線から標準偏差の2倍を引いた線です 。
見方・使い方:
- ボラティリティの把握: バンドの幅は、株価の変動幅(ボラティリティ)を示します。バンド幅が広いときはボラティリティが高く、狭いときはボラティリティが低いと判断できます 。
- 逆張り: 株価がアッパーバンドに近づくと買われすぎ、ローワーバンドに近づくと売られすぎと判断し、反転を狙う手法です 。
- 順張り(ブレイクアウト): バンド幅が狭まった後(スクイーズ)、株価がアッパーバンドまたはローワーバンドを大きくブレイクアウトした場合、トレンドが発生する可能性があると考える手法です 。
- バンドウォーク: 強いトレンドが発生している場合、株価がアッパーバンドまたはローワーバンドに沿って推移することがあります。これをバンドウォークといい、トレンドの継続を示唆します 。
5. 一目均衡表 (いちもくきんこうひょう)
一目均衡表は、日本で開発されたテクニカル指標で、相場の均衡状態を一目で把握できるように工夫されています 。トレンドの方向性、強さ、転換点、そして支持線・抵抗線の水準などを総合的に判断することができます 。
構成: 一目均衡表は、以下の5つの線と「雲」と呼ばれる帯で構成されています :
- 転換線: 過去9日間の高値と安値の中央値 。
- 基準線: 過去26日間の高値と安値の中央値 。
- 先行スパン1: 転換線と基準線の中間値を26日先行させたもの 。
- 先行スパン2: 過去52日間の高値と安値の中間値を26日先行させたもの 。
- 遅行スパン: 当日の終値を26日前にずらしたもの 。
- 雲: 先行スパン1と先行スパン2で囲まれた帯状のエリア 。
見方・使い方:
- 雲の位置関係: 株価が雲の上にある場合は上昇トレンド、雲の下にある場合は下降トレンドと判断します 。雲は、将来の支持帯や抵抗帯として機能すると考えられています 。
- 転換線と基準線のクロス: 転換線が基準線を下から上に抜ける(ゴールデンクロス)と買いシグナル、上から下に抜ける(デッドクロス)と売りシグナルとされます 。
- 遅行スパンと株価の位置関係: 遅行スパンが株価を上抜けると買いシグナル、下抜けると売りシグナルとされます 。
- 三役好転・三役逆転: 転換線が基準線を上抜け、遅行スパンが株価を上抜け、株価が雲を上抜けるという3つの条件が揃うと「三役好転」となり、強い買いシグナルとされます 。逆に、これらの条件がすべて逆になると「三役逆転」となり、強い売りシグナルとされます 。
まとめ
テクニカル分析は、過去の株価の動きを分析することで、将来の値動きを予測しようとする手法です。今回ご紹介した移動平均線、MACD、RSI、ボリンジャーバンド、一目均衡表は、数多くのテクニカル指標の中でも基本的なものであり、多くの投資家に利用されています。これらの指標は、トレンドの把握、売買タイミングの判断、相場の過熱感の認識など、様々な目的で活用することができます。しかし、テクニカル分析はあくまで将来の価格を予測する一つの手段であり、必ずしもその通りになるわけではありません。これらの指標を単独で使うのではなく、複数の指標を組み合わせたり、ファンダメンタルズ分析と併用したりすることで、より精度の高い投資判断を目指すことが重要です。株式投資においては、常にリスク管理を意識し、慎重な判断を心がけましょう。

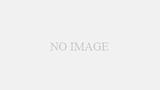
コメント